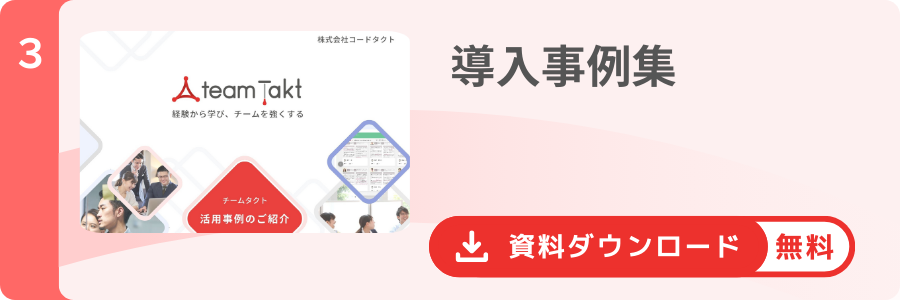「指示を待つばかりで自ら動けない」
「仕事の意義を見出せず柔軟性に欠ける」
「全体像を把握できず、チームワークに支障をきたす」
このような特徴を持つ社員は、いわゆる「指示待ち人間」に陥っている可能性があります。
社員を「指示待ち人間」から脱却させるためには、自ら考えて行動できる人材へ育てていく必要があります。その鍵となるのが「心理的安全性」です。
では、どのようにすれば部下の心理的安全性を高めることができるでしょうか。
本記事では「指示待ち人間」の特徴を紐解きながら、指示待ち人間に主体性を身に着けさせる方法を紹介します。
目次
指示待ち人間とはどんな人?
指示待ち人間とは一般的に「上司や同僚からの明確な指示がなければ行動に移せない、主体性に欠ける人材」を言います。
与えられたタスクには忠実に取り組むため真面目で従順にも見えますが、一方で想定外・突発的な事態に対処できません。その結果仕事の遅延につながったり、上司の負担が増大したりといった悪影響が出ることもあります。
このような「指示待ち」の傾向は、しばしば若手社員やいわゆる「ゆとり世代」の特徴として語られることがありますが、実際には年齢や世代に関係なく見られる現象です。
では、指示待ち人間の特性は変えられないのでしょうか。実は指示待ち人間は個人の性格だけでなく、経験や職場環境など、複合的な要因によって形成されます。
それではどんな人が「指示待ち人間」になりやすいのか、次項で詳しく見ていきましょう。
指示待ち人間になりやすい人の特徴
指示待ち人間になる背景はさまざまです。特徴を紐解いて見ていきましょう。
主体性が欠如している
主体性の欠如は、指示待ち人間の大きな特徴です。主体性が欠如する原因には大きく2つのパターンがあります。
1つは「何をすべきか考えてはいるが分からない」というもの。多くの場合は経験やスキルの不足に起因しています。もう一つは「そもそも考えようとしない(考えられない)」というもので、こちらは思考のプロセスやマインド、モチベーションに課題があるため、改善にはより多くの時間が必要です。
失敗を恐れている
失敗への恐れも大きな要因です。この場合、本人も「自分で考えて動く必要性は理解しているものの、失敗が怖く行動に移せない」といった心理状況に陥っていることがあります。
失敗を恐れているタイプの指示待ち人間は「自分の意見を言っていいのだろうか」「自分の考えは間違っているに違いない」といった否定的な自己イメージを持つ傾向にあります。その原因には「生育歴による自己肯定感の低さ」といった先天的なもの、また「職場の心理的安全性の無さ」といった後天的なものもあります。
他人に対して無関心
他者への無関心さも「指示待ち」の一因です。周囲に対する関心が薄いとコミュニケーションも必要最低限にとどまるため、チームの一員として主体的に行動する機会を逃してしまいます。さらに損得勘定が強い場合は最小限の努力で職務を果たそうとするため、追加の責任や業務を避ける傾向があります。
指示待ち人間が生まれる原因
指示待ち人間になる原因には大きく「職場環境によるもの」と「人生経験によるもの」があります。
職場環境による要因
職場環境による指示待ち人間が生まれる要因には、以下の3つがあります。
- 上司が高圧的な態度をとる
- 仕事の目的がわかりにくい
- 上司が代わりに仕事をやってしまう
上司が完璧を求めすぎたり、部下に不信感を抱いていたりすると「マイクロマネジメント」になることがあります。少しのミスに言及された部下は萎縮し、上司の機嫌を伺うことに心理的リソースを割くようになります。すると「新しい提案」といった主体的な行動はリスクとなり「指示待ち」でやり過ごそうとするのです。
また、明確な目標やゴールが示されていない場合も、目指すべき方向がわからないために責任感やモチベーションの障害となることがあります。
このように「先を見通せない・機会が与えられない・恐怖が先行する」といった職場環境では、自発的に行動するモチベーションを削いでしまうことがあります。
人生経験による要因
職場環境だけでなく、以下のような人生経験によって「指示待ち人間」となってしまうこともあります。
- 主体的に動く機会に恵まれなかった
- 失敗にトラウマがある
親や学校の先生に「こうしなさい」と指示をされて育った場合、自分で物事を選択する機会が乏しくなります。すると自ら考える習慣が身につかず、そのまま成人してしまうケースも少なくありません。
また、自発的に行動して失敗し、それについて怒られた経験があると、自分の選択や行動に自信を失ってしまいます。深層的には自発的に動きたい気持ちはあるものの、失敗のトラウマが原因で行動に制限をかけてしまうケースもあります。
【簡易診断】あなたの会社は大丈夫?チェックリストで指示待ち人間を生む職場診断!
「指示待ち」という状態は個人の資質だけでなく、上司や会社が“意図せず”作り出している構造的な課題が原因にあるかもしれません。
あなたの職場にいくつ当てはまるか、少しだけチェックしてみましょう。
もし、これらに心当たりがある場合、知らず知らずのうちに部下の主体性の芽を摘んでしまっている可能性があります。
▼チェックリストで、自社の「指示待ちリスク」を診断してみませんか?
資料ではチェックリストに加え、「指示待ち」が生まれる背景を深堀りし、4つの領域(組織文化・風土、制度・仕組み、マネジメント、経験・スキル)から具体的なデータも交えて解説しています。
✅️なぜ挑戦が生まれにくいのか?
✅️なぜ改善提案が出てこないのか?
✅️なぜ部下は本音を話さないのか?
✅️なぜ「考えられない」状態に陥るのか?
「良かれと思って」の取り組みが、なぜ部下の主体性を削いでしまうのか。その構造的な問題を解き明かし、自律的な組織への変革のヒントを探ります。
指示待ち人間を組織に所属させるデメリット
「指示待ち人間」は組織に以下のような悪影響を与えることがあります。
- 職場の生産性を下げる
- ほかの社員のモチベーションを下げる
- 直属の上司の評価を下げる
また、指示待ち人間を放置している会社に対して他の社員が反感を抱くことがあります。こうした不満が蓄積すると、組織の風土や管理体制への不信感につながるため、最終的には退職を検討する社員が出る可能性もあります。本人だけではなく、他のやる気のある社員や組織全体へも影響を及ぼしかねないため、指示待ち人間は改善させる必要があります。
次項からは、その改善方法について紹介します。
指示待ち人間の改善のポイント
指示待ち人間が生まれる原因から考えると、職場で以下のような環境を実践すれば改善に導けると言えます。
- 上司は部下の自主性を尊重し、サポートする
- 明確な目標やゴールを示し、仕事の目的を明らかにする
「上司が部下の自主性を尊重し、サポートする」ということは部下自身に、自分で決める機会を与えることになります。また、自身で決めたことを実行する機会も与えられます。「サポートする」というのは、失敗しても次の挑戦ができるようにする、精神的な支援の意味も含みます。ゴールを明示することで自身の仕事は会社の役に立っていると実感でき、モチベーションに繋がります。また、進むべき方向性が見えると「もっとこうしたら良いのではないか」という自発的なアイデアも考えやすくなるでしょう。
指示待ち人間の改善方法
指示待ち人間の改善のポイントは2つ、「部下の自主性を発揮できる環境をつくること」と「仕事の目的を明らかにすること」です。前者のポイントをさらに分解すると、
- 自身で決めさせる
- 実行(挑戦)の機会を与える
- 失敗によって精神的に傷つけられる恐れがないと安心を持てる環境をつくる
の3点になります。

心理学者のカール・ロジャーズによると、人が幸せを感じる瞬間は「自分のことを自分で決めている」という感覚がある時だとされています。1つ目のポイントである「自身で決めさせる」ことは、単に自主性を発揮させる環境づくりというだけでなく、自分で決めることで仕事にも前向きに取り組めるようになるため、成果が出やすくなります。
3つ目は「心理的安全性が高い状態」と言い換えられます。心理的安全性とは「組織やチームの中で、対人関係におけるリスクを冒しても大丈夫だと信じられる状態」です。自分が発言や行動をしても、否定されたり、罰せられたり、恥ずかしい思いをすることはないと信じられる状態を作ることで、部下は安心して自主性を発揮できるようになります。
自主性を育て成果を上げやすい環境を作るポイント「成功循環モデル」
心理的安全性が高い状態だと、成果が上がりやすいというメリットもあります。
MITで教授を務めていたダニエルキム氏が提唱した「成功循環モデル」をご存知でしょうか。成功循環モデルとは、「結果を出すためには、まずは関係の質を上げることが大切」という理論です。
教育の循環モデルでは、以下のような流れで結果が変化していくとされています。
- 関係の質
- 思考の質
- 行動の質
- 結果の質
上記から、成功循環モデルが悪循環に陥ると心理的安全性が下がり、好循環になると心理的安全性が向上するとされています。

「心理的安全性が高い状態」、つまり関係の質を改善することによって結果の質まで影響を及ぼすのです。
心理的安全性を高めるメリットが伝わったでしょうか。それでは心理的安全性を高め、自主性を育てるにはどうしたら良いでしょうか。そこで有効なのが「G-POPグループリフレクション(通称:G-POPぐるり)」です。
「指示待ち人間」から「自ら考え、動く」自律型人材へ変える【G-POPグループリフレクション(G-POPぐるり)】の流れ
G-POPとは
G-POPとは、中尾隆一郎氏が提唱する、「ハイパフォーマーの仕事の進め方」を体系化したもので
- Goal(ゴール・目的)を常に意識し
- Pre(事前準備)に時間を使い
- On(実行)しながら修正
- Post(振返り)から学ぶ
という4つのプロセスを繰り返すことで、パフォーマンス向上を図るフレームワークです。

1週間の業務をこのG-POPシートに記入し振り返ることで、Goal-Pre-On-Postのサイクルを実践することができます。このサイクルを回させることで、社員は失敗や成功のポイントを自ら学び、その学びを次週に生かすといった好循環を作れ、「成功の再現性を高め、失敗の再発防止に努める」振り返りによるセルフマネジメント力の向上が期待できます。
ぐるりとは
グループリフレクション(ぐるり)とは、ファシリテーターの進行に沿い、個人が経験したことや気付いたことを共有し、グループで対話を通じて内省(リフレクション)を深める手法です。
発表者が行った振り返りの内容に対し、他の参加者が感じたことを伝えることで他者の視点に触れ、新たな気づきや学びを得ます。テキストや口頭で言語化することでお互いの業務や考えに対する理解を深め、関係性を構築・強化します。チームタクトではぐるりを通じて、個人の内省力の向上と相互理解を深める場づくりを行う支援を行っています。

ぐるりでは全員に必ず5分ずつ発表する時間があるため、短い時間で的確に説明する能力が高まり、プレゼンスキルが向上します。また、他のメンバーの発表を聞く時間や、発表内容に対してコメントをする時間があるため、相手の話を聞くスキル、傾聴のスキルも向上します。
G-POPぐるりのメリット
G-POPぐるりを行うことは指示待ち人間改善のポイントを実行するだけでなく、「何をするかを自分で決める」「実行する」「結果を振り返り他者のフィードバックを受けて次に活かす」というプロセスそのものが「自律自転」の練習になるため、対象者に自立の感覚を掴ませることができます。
G-POPぐるりには以下のような効果があります。
- 周囲の期待を受けながら、成果を認め、お互いに成長を促せるようになる
- 「チームメイトに助けてもらえる」という安心感を持てる(心理的安全性の向上)
- 職場(チーム)のエンゲージメントが高くなる
- 主体性や顧客視点、自律性などが改善する
このように心理的安全性が高まった結果、指示待ち人間から脱却し「自ら考え、動く」自律型人材に成長できるのが特徴です。
G-POPぐるりをするなら「チームタクト」がおすすめ
G-POPぐるりの効果を最大限に引き出し、心理的安全性向上に役立つチームタクトの主な特徴を3つ紹介します。
①心理的安全性向上に:いいね、スタンプ機能
SNSのようないいね機能、よくできましたのスタンプ機能など、「褒める」機能があります。

こうした機能で褒め合うことで心理的安全性の向上を支援します。
②セルフマネジメント力向上に:振り返りAI分析機能
メンバーが行ったPost(振り返り)の記述内容を分析し、客観的な5つの指標で文章の傾向を確認できます。

部下はAI分析の結果から自分自身で、自分の思考の偏りに気づくことができ、多様な観点から思考できるよう、自ら改善していくことができます。
③マネジメントの効率化に:メンバーの関係性を見える化
G-POPシートはメンバー以外のシートも見られる状態になっており、他者のシートをよく閲覧している人ほど成長が早かったり、成長度合いが大きい傾向にあります。そこで、「誰が他者のシートをよく閲覧しているか」「誰が誰にリアクションしたか」といったアクションを見える化。行動の傾向を把握でき、ポジティブなアクションをとる社員をすぐに見つけられます。また、成長の判断だけでなく、心理的安全性の高い状態作りができているかを判断するツールにもなります。

まとめ
最後に、本記事で解説した「指示待ち人間」の改善について、重要ポイントをQ&A形式で振り返ります。
Q1. なぜ「指示待ち人間」になってしまうのですか?
A. 指示待ち人間は、本人の資質だけでなく、人生経験や職場環境によって作られる側面が大きいからです。特に職場においては、「上司が高圧的」「仕事の目的が不明確」「上司が先回りして仕事をやってしまう」といった環境が、部下の思考を停止させ、指示待ちの状態を助長している可能性があります。
Q2. 「指示待ち人間」を改善するポイントはなんですか?
A. 「自主性を尊重し、サポートする」環境づくりと「ゴールを意識させる」ことが大切です。自分で決める機会と実行する機会を与えつつ、失敗しても大丈夫だと思える「心理的安全性」を確保することで、部下は安心して主体性を発揮できるようになります。
Q3. 指示待ち人間を改善し、自律型人材を育てる具体的な手法はありますか?
A. 「G-POPグループリフレクション(G-POPぐるり)」が有効です。これは、自分で計画(Goal/Pre)を立てて実行(On)し、結果を振り返る(Post)というサイクルを繰り返す手法です。記事では、このプロセス自体が「自分で決めて実行する」ことの反復練習になると解説しています。また、グループで互いにフィードバックし合うことで「失敗しても大丈夫」という心理的安全性が育ち、安心して指示待ちから脱却できる土壌が整います。
本記事では、「指示待ち人間」になってしまう原因と改善策について解説しました。
社員を「指示待ち人間」から「自律型人材」へ変えていきたい方はG-POPぐるりを検討してみてはいかがでしょうか。ぜひ下記からお気軽にお問い合わせください。




.jpg)











.png)